光が街を変える。“きれい”なだけではない“意味ある光”へ、夜景のプロが語る「2025年のイルミネーション最前線」
全国
冬の訪れとともに、街のあちこちでイルミネーションが灯り始め、思わず足を止めて見入ってしまう。そんなイルミネーションの歴史と最前線を知り尽くすのが、夜景観光コンベンション・ビューロー代表理事であり、夜景評論家の丸々もとおさん。どんなトレンドが生まれ、今年の光はどんな変化を見せているのか。今シーズンのイルミネーションの動きを、丸々さんに聞いた。

個性が光る、進化するイルミネーション
ーー今シーズンのイルミネーションについて、今年ならではの傾向やトレンドをどう見ていますか?
【丸々もとお】2000年代初頭にLEDの価格が下がりだし、東京ドイツ村やあしかがフラワーパークなど、全国で本格的なイルミネーションが次々に誕生しました。それから20年以上の時が流れて、LEDの進化とともに光の表現もずいぶん多様化しました。かつては原色をたくさん使って、球数を競うような時代もありましたが、今はレーザーやプロジェクションマッピングなどを組み合わせた“演出の時代”に入っています。

ただ、なぜ多様化してきたかというと、日本人は良くも悪くも飽きやすいからです。飽きられないために、各施設が新しいことを次々に仕掛けてきた。その流れの中でコロナ禍もあり、観光業界全体が厳しい時期を迎えたものの、今は再び進化を求めるフェーズに入ってきたと思います。各施設が自分たちの特徴を見つめ直して、“どこを推しとしてファンを増やすか”を明確にし始めた。いわば“主体性の時代”です。
ーー各地の施設でも、それぞれの“個性”が際立ってきたように感じます。
【丸々もとお】たとえば伊豆のぐらんぱる公園では、巨大な龍のランタンを登場させています。これまでは中国製ランタンを並べるだけでしたが、今は自分たちで創り上げるオリジナリティの時代。単なる輸入ではなく、作品としてのスケールと創意を競うようになってきました。あしかがフラワーパークも同じです。アナログな美しさを大切にしながら、裏ではデジタルプログラムを導入して進化させている。東京ドイツ村も“光の地上絵”という自分たちの強みを活かして、鑑賞ポイントを増やし、より立体的に見える工夫をしています。

どこかの施設が人気だからまねをする、という時代ではもうありません。それぞれが“自分たちらしさ”を見つけ、個性を磨き合う時代に入りました。相模湖のイルミネーションでは「すみっコぐらし」「ポケモン」「ドラえもん」など、人気キャラクターを取り入れてIP戦略で勝負している。争い方そのものが変わったんです。
ーー個性化に加えて、“環境との共存”もキーワードになってきていますね。
【丸々もとお】そうですね。イルミネーションは電気を使うからこそ、環境への配慮が欠かせません。最近は低消費電力のLEDが主流になり、10メートルに100球巻くイルミネーションでも、従来の5ワットから1ワットに抑えられるものが出てきました。消費電力が5分の1になるわけです。こうした最新型LEDはまだ普及率が数%ですが、確実に未来を変える光だと思います。
沖縄の東南植物楽園のように“エコイルミ”を掲げる施設も増えています。限られた明かりでどうエンタメ性を出すか。環境と観光の両立をどう形にするか。そんな挑戦が全国で始まっている。イルミネーションが“きれい”で終わらず、“意味ある光”へと進化している証拠ですね。
見る人の“楽しみ方”が変わった
ーー仕掛ける側の進化に対して、見る側の楽しみ方も変わってきていますか?
【丸々もとお】そうですね。昔は“たくさん光っていればきれい”というシンプルな時代でした。でも今は、見る人たちも経験を重ねて目が肥えてきた。だからこそ、ただ眺めるだけでは満足しない。撮り方や見方まで、それぞれが工夫して楽しむようになってきたと思います。

みんな写真を撮るときに、肉眼で感じながら“伝えたい写真”を作るようになってきています。スマホで加工したり、光のエフェクトを入れたり。まるでプロ顔負けのテクニックで表現している。だから、作り手もどうとでも撮れるような光の設計を意識するようになりましたね。
ーーおっしゃる通り、SNSで見る写真のクオリティも上がっていますね。
【丸々もとお】ええ。でも実は、みんな意外と“後ろ”を見ていないんです。前を向いてワーっと歩きながら撮る人が多いけれど、後ろを振り返ると全然違う光の世界がある。作り手はストーリーの流れを考えて、背面にもこだわっているんですよ。だから、ちょっと立ち止まって後ろを見てみる。これだけで、他の人とは違う一枚が撮れます。
それからもう一つ、“撮らない時間”を持つことが大切です。まずはカメラを構えずに歩いて、空間全体を感じてほしい。夜は暗い分、地形の高低差や水面の広がり、木々の影が印象的に映る。丘の上や池のほとりなど、場所の特徴をつかんでから撮ると、まるで違う作品になります。イルミネーションの美しさは光だけじゃなく、地形との掛け合わせでも生まれるんです。
ーー確かに、最初から撮る前提で行くと、視野が狭くなりそうです。ロケハンが大事ということですね。
【丸々もとお】そうなんです。まず感じることが大事。撮る前に“ロケハン”するような感覚で見てみると、発見の質がまるで違う。プロのカメラマンは、いきなり撮り始めない。まず現場を見て、構図を考えてから撮る。だから、自分だけの“見つけ方”を楽しむことが、イルミネーションの新しい楽しみ方だと思います。

そして、忘れちゃいけないのが防寒(笑)。冬の夜は冷えるから、温かい飲み物を片手に、ゆっくり歩きながら光を味わう。焦らず、のんびりと。光は逃げませんから。
日本三大イルミネーション再認定と総選挙の舞台裏
ーー今年は「日本三大イルミネーション」の再認定も話題になっていますね。
【丸々もとお】はい。今年は特別な年です。全国6600人以上の夜景観光士が、1000カ所を超える夜景やイルミネーションイベントに投票し、その結果に一般投票を加えて上位3カ所を選びます。これが“日本三大イルミネーション”です。

これまで認定されていたのは「札幌」「あしかがフラワーパーク」「ハウステンボス」ですが、7〜8年ぶりの再選定を迎えるタイミング。今回は東日本・中日本・西日本の3ブロックで地区ランキングを出して、最後に“決選投票”でトップ3を決める。言ってみれば“イルミネーション総選挙”ですね。
ーーまるで全国大会のような盛り上がりですね。
【丸々もとお】そうなんです。エリア分けにも工夫があります。東日本と西日本の2つでは東海エリアがどちらに属するのか曖昧になってしまう。なばなの里、時之栖、伊豆ぐらんぱる公園、ラグーナテンボスなど、強力な施設が集中する地域だからこそ、中日本ブロックを用意しました。

まず東・中・西の順にランキングを発表し、最後に上位3つで“最終決戦”。メジャーリーグのプレーオフのような形式で、最終的に「日本三大イルミネーション」が決まります。その発表の舞台が、2025年11月27日(木)に藤沢で開催される夜景サミットです。
ーー選定のポイントにはどんな基準があるのでしょうか。
【丸々もとお】単に“明るい”や“規模が大きい”というだけでは選ばれません。私たち夜景観光コンベンション・ビューローでは、7つの認定項目を設けています。
1つ目は、敷地を活かしLED照明を効果的に使っていること。2つ目は、エンターテインメント性に富んでいること。ほかにも、オリジナリティや回遊性、運営スタッフの情熱、サービス面の充実など、多角的な視点で審査しています。美しさはもちろん、観光としての魅力や地域の活性化に貢献しているかどうかも大切なポイントです。
地方の夜に息づく光、大都市が仕掛ける未来の光
ーー新・日本三大イルミも気になりますが、日々、全国の夜景やイルミネーションを見ているなかで、丸々さんは今後の夜景・イルミネーションの広がりについてどう考えていますか?
【丸々もとお】今、ようやく“大都市が動き始めた”と感じています。これまで夜景といえば長崎や神戸、函館のような観光都市が中心でしたが、東京や横浜、名古屋のような大都市もナイトタイムエコノミーに本格的に取り組み始めました。東京都は観光財団が助成を行い、公園での夜イベントも増えています。横浜も市長が“夜の魅力を伸ばす”と掲げ、動きが活発になっているんです。

一方で、地方都市は財源が厳しく、苦戦もあります。税収が豊富な政令指定都市が参入してくると、スケールでは敵わない。でも地方には歴史や文化といった“光を当てる資源”がある。地方だからこそできる、歴史を活かした光の演出。これが地方の強みです。
ーーなるほど。戦い方が違うわけですね。
【丸々もとお】そうなんです。大都市は資金力、地方は歴史や風土。どちらにも違った魅力がある。東京のように新しいビルや観光資源が中心の街では、どうしても歴史的な空間を活かす余地が少ない。でも地方にはまだ眠っている文化財や史跡が多くあります。そこに光を当てるだけで、新しい夜の観光資源になるんです。

だからこそ、外部の人や新しい発想を積極的に取り入れることが大切。地方には“外の人を入れたくない”という空気がまだ残っているところもありますが、柔軟に考え、外の力を取り込めばもっと強くなる。夜景やイルミネーションは、その地域の文化や人の心を照らすもの。だからこそ、オープンマインドで取り組むことが未来の光になると思います。
未来への光と、日本が世界に発信する技術力
ーーこれからの10年、20年。イルミネーションや夜景の文化はどんな方向に進んでいくと考えていますか?
【丸々もとお】これからは、“光を輸出する時代”になると思います。今までは日本の技術で観光客を呼び込むという内向きの発想でしたが、これからは日本の技術を世界へ持っていく時代。たとえばLEDやプロジェクションマッピング、ドローン演出のように、日本発の技術が世界を席巻した時代がありましたよね。その第二章が今、始まろうとしています。

日本には実験的な環境があります。規制が厳しい分、精度や安全性の高いデータが取れる。たとえば私が関わっているラグーナテンボスの「光の花手水」なんかはまさにそう。イルミネーション演出にドローンを加えた世界でも類を見ない挑戦です。こういう試みを日本で成功させれば、次はラスベガスでもできる。技術の輸出につながります。
ーー観光が技術開発や産業育成にもつながっていくと。
【丸々もとお】そうです。観光は受け入れるだけの産業ではありません。技術を磨き、発信することで新しいビジネスになる。日本の夜景やイルミネーションは、世界市場で十分勝負できるレベルにあると思っています。青色発光ダイオードの発見によりLEDが加速度的に広まったように、世界を変える力がある。だからこそ、若い世代にも“攻めの発想”を持ってもらいたいですね。
ーーインバウンドが回復してきた今こそ、次のステップが必要なんですね。
【丸々もとお】そう。今の日本は、観光客を受け入れて満足してしまっている。でも本当は、そのデータや経験を次のステージに活かすべきなんです。外国人観光客の嗜好や行動データを分析すれば、次に何が求められているかが見えてくる。それを踏まえて、新しい演出や技術を開発し、世界に輸出していく。観光を“輸出産業”に変える発想が大切だと思います。

ーーつまり、夜景もイルミネーションも、“未来を照らす産業”になり得ると。
【丸々もとお】まさにその通りです。光は人を笑顔にするだけでなく、街を動かし、経済を動かす。だから私は、夜景やイルミネーションを“希望のインフラ”だと思っているんです。どんな時代でも、人は光を求める。その原点を忘れずに、これからも新しい技術と発想で日本の夜を輝かせていきたいですね。
みんなで選ぶ”新しい日本三大イルミネーション
丸々さんの言葉に共通していたのは、“光が街と人をつなぐ力”への信頼だった。技術の進化、環境への配慮、そして地域の個性。すべてが調和した時、そこに新しい夜の風景が生まれる。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
取材=浅野祐介、取材・文=北村康行、撮影=阿部昌也
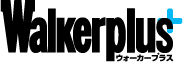
全国のイルミネーションを探す
| 全国の人気イルミネーションランキング |
| 全国の行ってみたいイルミネーションランキング |
| 全国の行ってよかったイルミネーションランキング |
開催状況から探す
都道府県からイルミネーションを探す
イルミネーションガイド
おすすめ情報
人気イルミネーションランキング
【全国】
閲覧履歴
- 最近見たイルミネーションのページはありません。
イルミネーションをもっと楽しむ
-
 【2025年】東京の人気イルミネーションランキング!都会の夜がロマンチックに輝くイルミの世界へ
【2025年】東京の人気イルミネーションランキング!都会の夜がロマンチックに輝くイルミの世界へ -
 【2025年】大阪の人気イルミネーションランキング!大阪で美しく輝くイルミを見に出かけよう
【2025年】大阪の人気イルミネーションランキング!大阪で美しく輝くイルミを見に出かけよう -
 おすすめのクリスマスマーケットイルミネーションとともにクリスマスのお買い物を楽しもう!
おすすめのクリスマスマーケットイルミネーションとともにクリスマスのお買い物を楽しもう! -
 東京周辺のクリスマスマーケット東京クリスマスマーケットや赤レンガ倉庫など人気マーケットをピックアップ
東京周辺のクリスマスマーケット東京クリスマスマーケットや赤レンガ倉庫など人気マーケットをピックアップ -
 「日本三大イルミネーション」とは?日本最大規模のイルミネーションを紹介!
「日本三大イルミネーション」とは?日本最大規模のイルミネーションを紹介! -
 イルミネーションデートなら!冬のデートスポットにおすすめ!東京都内のイルミネーション
イルミネーションデートなら!冬のデートスポットにおすすめ!東京都内のイルミネーション -
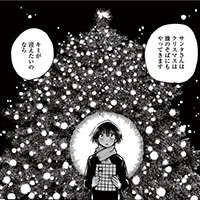 おすすめ「デート」「恋愛」漫画特集5選!教えたくなるクリスマスの豆知識からデートあるあるまで!
おすすめ「デート」「恋愛」漫画特集5選!教えたくなるクリスマスの豆知識からデートあるあるまで! -
 イルミネーションランキングアクセス数の多かった人気イルミネーションをエリア別にランキング
イルミネーションランキングアクセス数の多かった人気イルミネーションをエリア別にランキング -
 イルミネーショントピックス人気のイルミネーションの見どころ、イベント情報など楽しみ方をご紹介
イルミネーショントピックス人気のイルミネーションの見どころ、イベント情報など楽しみ方をご紹介 -
 イルミネーションカレンダー今、開催中のイルミネーションを日付から探す
イルミネーションカレンダー今、開催中のイルミネーションを日付から探す



